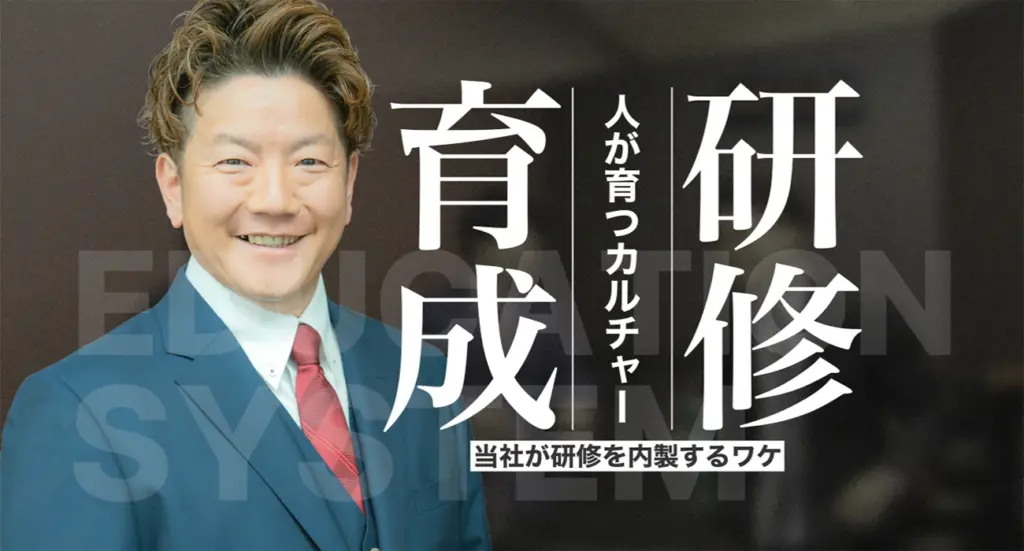
新卒の方はもちろん、未経験で中途入社をする方も、入社後の教育体制がどうなっているかはとても気になるはず。ということで、今回は当社の“強みでありカルチャーの一環”でもある「入社後研修」に焦点を当てていこうと思います。

文系未経験でも入社しやすくなったIT業界
前提として、昔に比べるとIT業界へのチャレンジは格段にしやすくなっています。また、一般的には“入社後の研修を社内で行うことが当たり前“、というイメージがあると思います。ところがこの業界では、未経験の方を社内でじっくり育成する環境が整った会社ばかりではないのです。
では、具体的にどう教育するかというと“研修を外注している”ということです。平たく言えば、研修事業を専門に行なっている会社があり、そこに依頼をして新人の育成をしてもらうというわけですね。
外部に頼る理由や課題
では、なぜ外部に研修を委託するかですが、まずはメリットからご説明していきます。そもそも、社内で工数を割かれないので効率がいい点や、研修の品質が担保されている点が主なメリットです。一方で、社内に育成するリソースを持っていない、教育に人を割くことができない、教えるノウハウがないといった理由から依頼する企業が多いわけですね。
「人を伸ばす」ための研修について考える
外部研修の場合、そのほとんどは他社の新入社員と合同で集団実施をする形なんですね。パッケージとして組まれた研修カリキュラムに沿って、足並みを合わせながら進んでいくため、1人ひとりの習熟度に焦点が合わせづらい傾向です。ところが、習熟度は千差万別。早い人もいれば遅い人もいますし、理解が深い人もいれば浅い人もいますから、要はそこに”どこまで合わせながら習熟度を高めさせていけるか”が重要なのではないか、と当社では考えています。
また、エンジニアとして長く活躍するためにとても大切なのが“継続して学習し続ける”というルーティンを形成することです。「学習しなくちゃ」といったマインドを醸成することが、伸びる人材育成の基礎だと思います。

当社が研修の内製にこだわる理由
社内で研修を実施する狙い
狙いはいくつかありますが、まずITエンジニアの仕事はただプログラミングができればいい仕事ではありません。そこにはビジネスマナーも必要ですし、コミュニケーションも不可欠です。だから当社では、新入社員が“現場配属後に携わるだろう実務”に近い実践的な内容を実施しています。わからない時にはどう振る舞えばいいか、どのように先輩に質問したらいいか、周りのメンバーとどう連携したらいいかというところを、体験を通して学ぶことがとても大切だからです。
もう1つ。例えば外部研修では、入社後すぐに所定の場所に通って研修を受講しますので、たとえば研修期間が3ヶ月だとした場合、本来4月入社だったとしても実質の入社は7月の感覚になります。さらに、プロジェクトに入ってお客様先に通勤することになれば、社内の人たちと関わる機会もほとんどないかもしれません。
その点、社内で実施する研修なら先輩や同期とのコミュニケーションも取れますし、交流機会が増えることで働きやすさや安心感も増します。また、役員や先輩社員からしても、皆さんの強みや特性を理解する期間として、とても重要な時間だと認識しています。
実際に実施する研修内容
開発エンジニアと運用エンジニアでは、実施する内容はもちろん異なります。
開発エンジニアの研修内容は(未経験の中途入社。ITエンジニアに転職してからデビューするまでの道のりと中身について)で詳しめに紹介していますので、ぜひあわせてお読みいただければと思っていますが、簡単に説明すると実務を模した業務システム、WEBシステムをイチから作っていきます。
とはいえ、大きいものを期間内でドーンと作るわけではなく、まずは基礎的なところから入って1つ目の小さな課題、2つ目の課題、3つ目の課題といったように、徐々に難易度を上げつつ何度も繰り返しながら学習して慣れていく。という流れで進めていきます。
運用エンジニアでは、ネットワークやサーバーなど、インフラ分野の技術学習をしていきます。早い段階からOJT教育が中心になる点も、開発エンジニアの研修と大きく異なる部分ですね。
また、先ほど「継続して学習し続けること」が大切だとお話しましたが、当社ではその土台づくりとして、入社1年未満にJavaの資格、SQLの資格、基本情報の資格取得を目標に取り組んでもらっています。これらを達成するための学習スケジュールを立てて、計画的に学習をしながら学習ルーティンの形成を促しています。
自社内研修の強みや他社との違い
研修内容の柔軟なアップデートが行えるので、そこは強みだと感じていますね。もっと具体的にいうと、研修を明けたメンバーがプロジェクト先に配属後、実務を通して感じたことを意見としてもらい、「こういうところを重点的に教えてもらえるとよかった」などの気づきを回収して、それを元に研修内容を改善するという感じです。外部研修ではカリキュラムを柔軟に変更するといったことはなかなかできないと思うので、差別化になるのではないかと思いますね。
他の強みでいえば、技術以外にビジネスマナーなども並行して教育できる点です。先輩たちがすぐ近くで見てくれていますので、対策や改善も即座に行えるのは間違いなく強みだと思います。
その人に合ったフルカスタマイズな研修
集団研修では難しい“個別カスタマイズ”ができるので、皆さん各自の習熟度や個性に合わせた育成方法や手段が取れるのは、研修を内製化しているからこそできることです。
さらに言えば、分からないを分かるに変えるだけでなく、分かるからこそもっとレベルの高い課題にも挑戦できる、といった「+αの部分」を作ったり変更したりもできますからね。
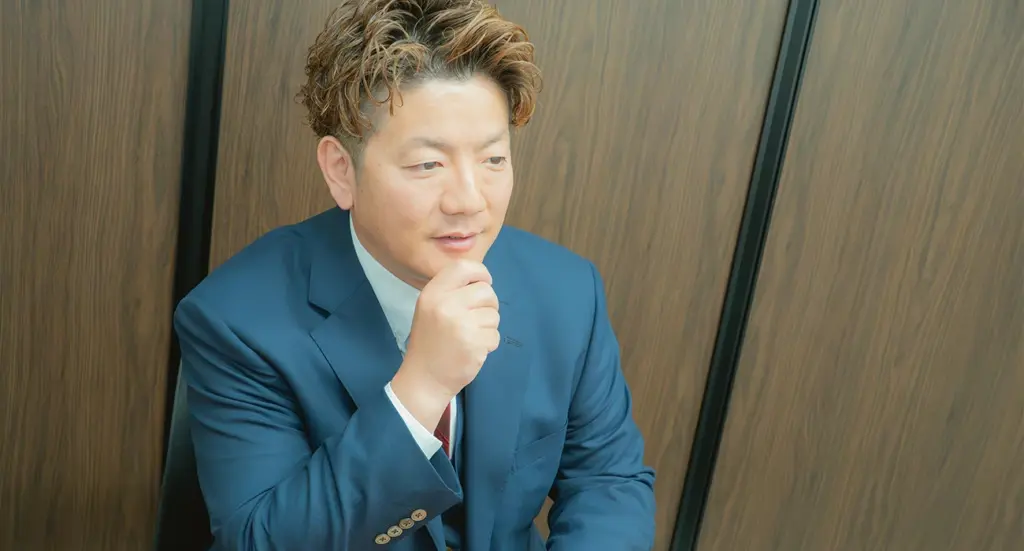
人が育つ仕組み=当社のカルチャーでもある
自然発生する教え合いの文化
多くの同業他社の場合、1日の仕事を終えたエンジニアは、お客様先を出た後そのまま帰宅します。当社は、自社オフィスに常勤しているメンバーもいますし、業務後に帰社するメンバーもいます。なので、研修を受けている新入社員を気にかけたり、分からないところを教えてくれたりといった光景が自然に発生しています。先輩たちもそうしてもらった経験があるから、自分も「後輩の力になってあげたい」といった思いが根付き、 “教え合いの文化”が形成されたのだと思いますね。
社内でのコミュニケーションも間違いなくカルチャー
研修担当がオフィスに常勤するようになったり、採用チーム発足など社内で取り組む事柄が増えたことにより、オフィスに出入りするメンバーが増え、コミュニケーションをする頻度や機会が増えたことが、当社のカルチャーをより強固なものに変えているような気がします。本当にみんな仲がいいですよ、ご飯の待ち合わせでオフィスを集合場所にしたりするほど。だから、オフィスに戻ってくるということはみんなにとって、ごく自然かつ日常の一コマといった感覚なのかなと感じでいます。
教え合いのDNAをつないでいく
現場に配属されたあとも、チームの先輩にさまざまなことを教わっていきますが、ただ教わるだけではなく、自らも自発的に学びにいく行動が必要です。再三お話しましたように、ITエンジニアとして長く活躍するためには持続的な学習が必須です。だから、リーダーや先輩も含めてみんな勉強の身なのです。後輩に教えるということは、自分たちの気づきや理解の深まりにもつながりますからね。
だから、皆さんも先輩たちから教えてもらったことを、今度は後輩に対して教えながら再確認したり、自分の弱点に気づいたりして、新たな学びを得ていってもらえるといいなと思います。
・・・・
さいごに
いかがでしたでしょうか。この記事をお読みいただくことで、当社が入社後研修の内製にこだわる理由や、それらがもたらしている社内カルチャーについて知れたのではないかと思います。「なんだか自分、日本事務処理サービスのカルチャーにフィットしそうだな」と感じていただけたなら、ぜひエントリーお待ちしています!
エンジニア採用 エンジニア適性 ガジェット キャリアパス クロストーク システムエンジニア スマホアプリ プログラマー プログラミングスクール プロジェクト先 ランチ リファラル採用 ロケーション 中途採用 営業採用 座談会 採用チーム 文系エンジニア 文系出身エンジニア 新卒入社 未経験入社 理系出身エンジニア 研修制度 育児休暇 資格



